活動情報
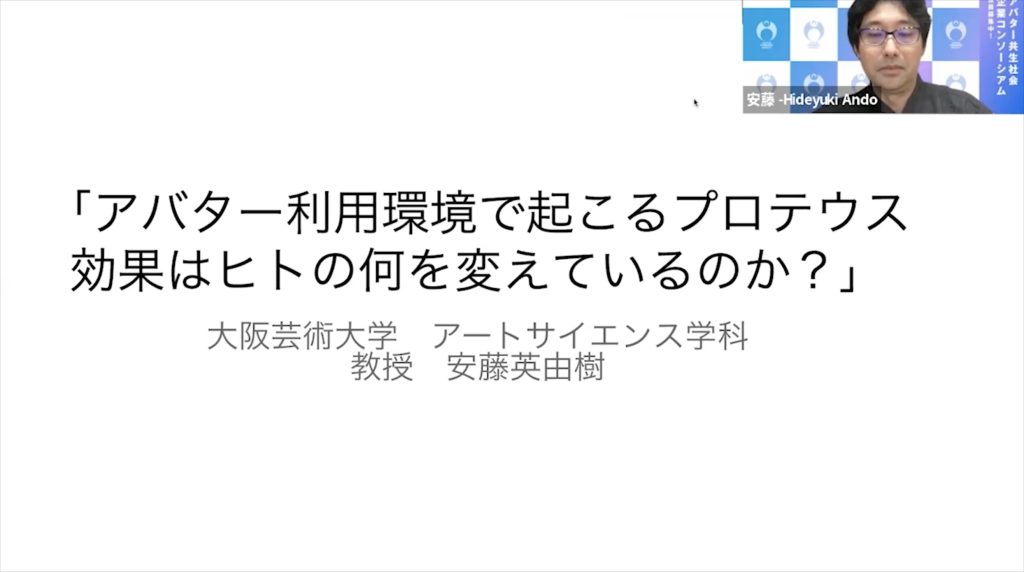
第2回交流会【レポート】心理効果からみるアバター活用の可能性(7/25開催)
サイバネティックアバター※による誰もが自在に活躍できる社会(アバター共生社会)の実現に向けて、第3回の情報交流会が開催されました。
今回は、心理効果からみるアバター活用の可能性と題して、バーチャルアバターにおける見た目がユーザーの行動特性に影響を与えるとされる心理効果である「プロテウス効果」について紹介しました。
※遠隔操作ができる「身代わりロボット」
PROGRAMプログラム
7月25日(月)開催
- 16:00~ :研究開発スケジュール
- 16:15~ :アバター利用環境で起こるプロテウス効果はヒトの何を変えているのか?
- 17:15~ :ディスカッション
REPORTレポート
サイバネティックアバター共生社会企業コンソーシアム研究開発スケジュール
国際電気通信基礎技術研究所 インタラクション科学研究所所長
アバター共生社会PJ研究開発項目7(実社会実証実験)課題推進者
宮下 敬宏 氏
会の冒頭は宮下氏から。本コンソーシアムの研究開発についての概要とスケジュールについて、ムーンショット研究開発プロジェクトの全体像を交えて、話しました。
アバター利用環境で起こるプロテウス効果はヒトの何を変えているのか?
大阪芸術大学アートサイエンス学科教授
安藤 英由樹 氏
メタバースなどのアバター利用環境のなかで、ユーザ(本人)と属性の異なる場合には、ユーザ(本人)の本来のアイデンティティにも変容を及ぼす可能性があることが、実験で確認されています。
この効果は「プロテウス効果」と呼ばれています。
この「プロテウス効果」についての一般的な解釈と、安藤氏が考える利用可能性について、解説しました。
メタバース空間で起こるプロテウス効果として挙げられることは、大きく2つ。
・対人距離
姿が魅力的な条件の参加者の方が、歩み寄る距離が近い。
・自己開示
姿が魅力的な条件の参加者の方が、高い自己開示性を示し、自分自身に関するより多くの情報を提示する。
背の高いアバターを着た参加者は、自信に満ちた行動をとり、積極的に交渉に臨む。
また、アバター使用後も現実の環境でもその傾向が一定期間維持されるという論文について話しました。
メタバース空間に入る前に、身体とアバターをつなげる作業をすることが、より深い没入感を得るために必要であることが実証でわかってきたという論文についての説明がありました。
具体的には、実験者が身体に機具を装着し、メタバース空間に入る前に、身体を動かすとアバターの身体が同期して動くことを視覚的・触覚的に確かめる作業を行います。
安藤氏は「アバターが視覚的だけでなく、身体的に乗り移ったという感覚を無意識に近いレベルで行うことが、高い没入感を得るポイントなのだと思う。」と話しました。
・アバターによってできるかもしれないこと
「学生の間で、議論が怖いという人が増えている」というニュースがあります。
議論中に自分の意見が否定されると、自分が否定されているわけではないこととわかっていても、心理的負荷が大きくかかってしまうから、議論ではなく多数決で決めたい、という学生が増えてきているといった内容です。
安藤氏「これらの問題に対して、アバターを介して議論をすれば言いにくいことも言いやすく、意見を言われても受け止めやすいのではないか。アバターが心理的負荷を吸収できるのではないか。」とアバター活用の可能性について語りました。
さいごに
今回の情報交流会では、仮想空間を語るときに必ず出てくるキーワード「プロテウス効果」について、深掘りをしました。 少しでも「アバター市場」の創出に向けてのビジネスヒントになれば幸いです。
情報交流会は定期的に実施しています。
情報をキャッチしたい方は、iRooBOセミナー・イベントページでチェックしてください。
-----------
<参考>
ムーンショット型研究開発事業
「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」
※本プロジェクトに参画したい企業様団体様、お待ちしています。